終端した結合伝送線路のクロストーク波形(RS=RT=Zg)
前々項の終端した結合伝送線路のクロストーク波形(RS=Z0,RT=∞)では、クロストーク波形の式を次の条件で簡単な形にできた。
(1) 受信端はハイインピーダンス(RT=∞) すなわちΓT+=ΓT-=1
(2) TEM波だとしてevenモードとoddモードの伝搬速度は同じ(τ+=τ-=τとおく)
このうち条件(1)を
(1') 送信端と受信端を同じ抵抗値(RS=RT=R)で終端する。すなわちΓS+=ΓT+ =Γ+ ,ΓS-=ΓT-=Γ-
に変えても簡単な形になる。
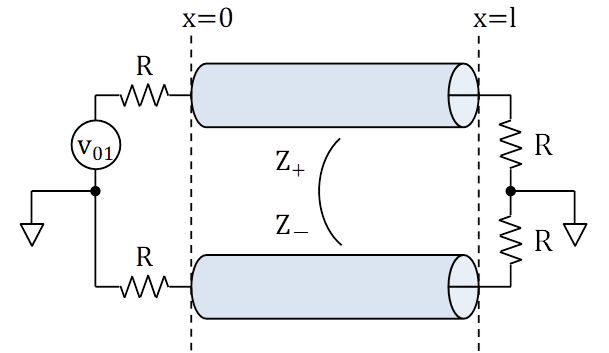
◇
条件(1')(2)を適用すると、式はv01でくくれて簡単な形に整理できる。
【能動側】
![]()
![]()
【受動側】
![]()
![]()
◇◇
ここで前項で示したように、RをZ+とZ-の相乗平均になるように選ぶと
![]()
になるから
【能動側】
![]()
![]()
【受動側】
![]()
![]()
これらの第1式と第4式から次のことがわかる。すなわち、結合伝送線路を送受信端共にR=√(Z+Z-)で終端したとき、能動側は送信端のクロストークノイズがなくなり、受動側は受信端のクロストークノイズがなくなる。ただし、実際の設計でこのような条件を使うことはないように思う。
◇◇◇
この式を使って波形を描いてみる。
前々項と同様に、反射係数を、クロストーク係数ξとRをZ0でノーマライズした無次元パラメータ
![]()
を使って書き直すと
![]()
ここでRはZ+とZ-の相乗平均になるように選んだから
![]()
この値を代入すると
![]()
結局、反射係数はパラメータξによって決まり次のグラフのようになる。
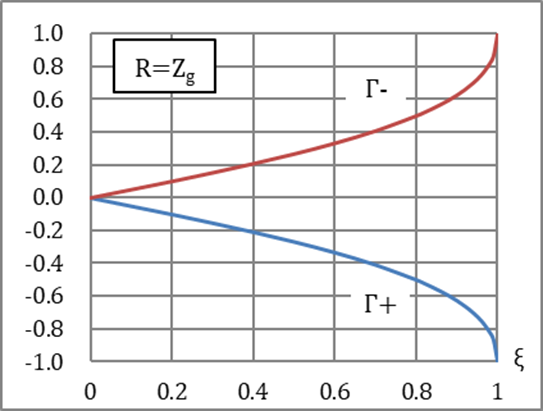
能動側の入力波形は、振幅1、立ち上がり時間tr=0.5τの台形波形とし
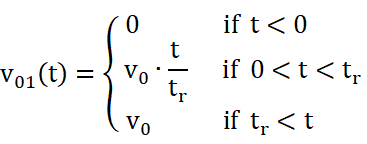
パラメータは前々項と同じξ=0.4として、Functionviewerで波形を描くと次のようになる。(赤が能動側、青が受動側)
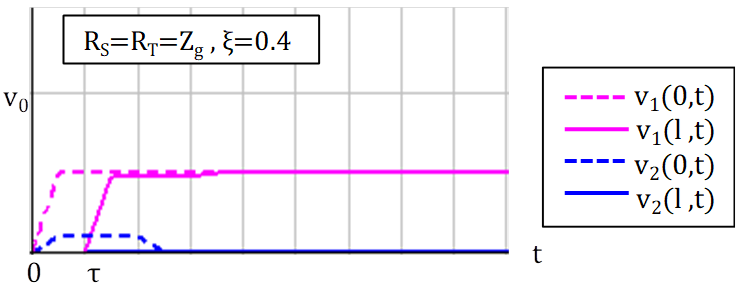
前々項のRS=Z0,RT=∞のときの波形と比べると、クロストークは小さくなっている。
◇◇◇
上記の式を時間経過ごとの振幅がわかる形に書き換える。次の恒等式を使って隣接する項どうしをくくると
![]()
【能動側】
![]()
![]()
【受動側】
![]()
![]()
ここで能動側の入力v01(t)がステップ波形だとすると
![]()
v01(t-nτ)-v01(t-mτ)は時間 nτ< t <mτの振幅を表しているので
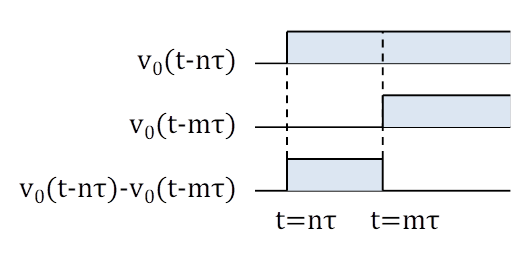
時間経過ごとの振幅は次のようになる。
【能動側】
![]()
![]()
【受動側】
![]()
![]()
|Γ|<1であることに注意すれば、クロストークの振幅は急速に減衰していくことがわかる。
一番大きい最初(n=0)のパルスに注目すると
![]()
となり、前々項と同じ程度の振幅になっている。